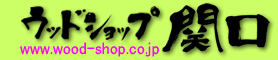

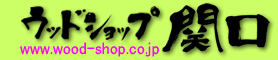 |
 |
| <<HOME| | 木材販売| | ご利用案内| | 運賃について| | 木の知識| | 作品例| | |FAQ | お問合せ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ■ はじめに湿気環境の重要性 |
| 児童を対象とした最近9年間の調査によると、身体的因子としての「アレルギー素因」の保有率が51.7%に達し、 |
| 実に2人に1人の割合になったという報告があります。アレルギー疾患の原因としてはさまざまなものが挙げられ |
| ていますが、なかでも住まいの湿気環境については、アレルギー性気管支炎、アレルギー性鼻炎などの発症に |
| 関係があるとされているダニ、カビやハウスダストの生育形態または発生量に、深い関係をもつという調査報告も |
| あります。最近になって、住まいの環境の健康性が問題になり、シックハウスという言葉までしばしば聞かれるよ |
| うになりました。私達の住まいは、過去約50年の間に、いろいろな事情で高気密化されてきました。その上、伝統 |
| 的な我が国の住まいで使われてきた土壁、無垢板の天井、畳、障子道具、襖、板床、土間などの天然素材による |
| 造作は、建築コストや工期の縮減のために、工場生産された人工材料によって次第に置き換えられていきました |
| 。このような呼吸性に乏しい材料で内装された高気密の住まいで通風や換気を適切に行わないと、結露が生じる |
| のは当然のことです。過去50年間の日本の住まいの環境の変化は、見方によっては、次々と生じるさまざまな結 |
| 露被害とその対策の繰り返しであったと見ることさえできます。ところが最近になって、これまでの高湿度環境と |
| はまるで反対の極度の乾燥状態が、住まいで発生するようになりました。高気密化された住まいと住み手による |
| 換気不足の住まい方に、都市大気の乾燥化、ホームエアコンや床暖房設備の普及などの影響も加わって、住ま |
| いの湿気環境に過乾燥現象が現れるようになったのです。先年のインフルエンザ流行の折に、介護施設などで |
| 高齢者が集団的に亡くなった事件は記憶になお新しいところですが、こうした極度の低湿度環境下でのウイルス |
| 感染を考えると、住まいの湿気環境は私どもの健康や生命にいろいろな点で深くかかわっていると考えざるを得 |
| ません。室内空気の極端な高湿度や低湿度を抑制する内装材料として、最近「調湿建材」が注目されるようにな |
| ったのも、そういした住まいの湿気環境に対する関心の高まりによるものといえましょう。 |
| この特集では、湿気環境を通して住まいの健康を考え、これまで使われてきた天然素材や、それらの吸放湿性を |
| 見てみます。 |
| ■ 世界の気候から見た日本の湿気環境 |
| 蒸し厚い日本の夏。夏は地球上どこでも湿度が高いと思ったら、ヨーロッパは反対で、夏、湿度が低く、冬、湿度 |
| が高くなるのです。アジア・モンストーン地帯とヨーロッパの主要な都市の気候図(クリモグラフ)を比べてみると、 |
| その様子がよくわかります。(図1、2)。気候図は、月平均湿度を横軸に、月平均気温を縦軸にとって1月から12月 |
| まで順につなぎ合わせたもので、その土地の気候を一目で理解するためにはなかなか便利な図です。気候図の |
| 範囲を広げて、世界の特徴のある土地の気候を見たのが図3です。その土地の気候状態を表す図形が四隅に近 |
| づくほど、それぞれ焦熱、蒸暑、刺寒、湿冷的な過敏な環境風土ということになります。このように地球上の気候 |
| はまことに多様です。冬の暖房期間が長いヨーロッパの国々に比べて、一部の地方を除けば比較的温暖な日本 |
| では、住まいの湿気環境対策や外断熱か内断熱かといった断熱構法を考える場合にも、こうした気候風土の違 |
| いを十分考慮しなければなりません。国際化時代にも、それぞれの環境風土に合った住まいづくりが必要です。 |
| ■ 北海道の夏はなぜ爽やかなのか |
| 夏の北海道は湿度が低く空気が乾燥しているから凌ぎやすいと言われていますが、この場合の湿度は私たちが |
| 日常使っている相対湿度という単位で表した湿度に関係があります。 図4のように横軸に緯度をとり、縦軸に8月 |
| の月平均相対湿度をとってみると、むしろ北海道の方が九州や沖縄よりやや高いくらいです。しかし、絶対湿度と |
| 緯度の関係で見ると、図5のように明らかに沖縄に比べて北海道の空気の方が乾燥していることがわかります。 |
| 相対湿度も絶対湿度も空気中に含まれている水分の量を表したものですが、相対湿度は空気中の水分の割合 |
| を飽和状態を100としてパーセントで表しているのに対して、絶対湿度の方は通常1立方メートルの大気中に含ま |
| れている水分の重量で表しています。したがって、相対湿度が同じ70%でも那覇と稚内では気温が違うために空 |
| 気中に含まれている水分の量は大きく異なることのなります。人体への影響や物の保存などには相対湿度だけ |
| でなく、この絶対湿度も重要な関係を持つことを憶えておいてください。 |
| ■ 住まいの湿気環境の変化 |
| 日本は南北の細長い国土の周囲を海に囲まれていて、1年を通して湿度が高く、暖流と寒流の影響を交々受け、 |
| 北は亜寒帯から南は亜熱帯に及ぶ、多様でしかも四季の変化に富んだ気候風土となっています。したがって、日 |
| 本各地には、古くからその地方の環境の下での長年にわたる暮らしの知恵から生まれたさまざまな形態の住ま |
| いが伝えられてきました。そしてそれらの住まいを形づくっていたものは、土と石と草木といったすべて天然の素 |
| 材でした。そうした伝統的な日本の住まいの形態は、さまざまな原因によってわずかこの50年の間に大きく変化し |
| ました。住まいの結露被害が最初に社会問題となったのは、戦争間もない1949年のことです。当時技術導入され |
| た空洞コンクリートブロックでつくられた北海道営住宅で激しい結露被害が起きたのです。そのため、北海道庁が |
| 日本建築学会に調査を委託し、1950年から約3年をかけて検討した結果、米国住宅総丁資料の翻訳と、それに基 |
| づく防露、防寒、換気、暖房計画指針が提出されました。これが我が国における内断熱工法と防露工法提案の最 |
| 初となりました。その後、全国各地のコンクリート造集合住宅での、壁の内表面や最上階の屋根スラブ下への結 |
| 露被害の発生などが契機となって、住宅公団がさきがけとなり、次第に断熱材料が使用されるようになりました。 |
| ただし、戸建住宅に断熱材料が使用されるようになるのはもう少し先のことです。 |
| 1960年代になって、高度成長にともなう公害発生やその後に続く2度のオイルショックを引き金に、住宅産業の発 |
| 展と工場生産品としての新建材の開発、普及、建築施工精度の向上などによる影響が加わって、一挙に日本の |
| 住まいの高気密高断熱化と画一化が進行しました。この間、排気ガスを直接室内に排出する直排型の家庭用燃 |
| 料暖房器の普及による酸欠・爆発事故や、激しい結露被害の発生などが見られるようになり、また、最近では、ホ |
| ームエアコンや床暖房設備の普及による新しい湿気環境問題として、住まいの過乾燥現象がホームダストやダ |
| ニ相の変化などを一因とするアレルギー疾患の急増といった現象と関連して、私たちの住まいの健康に大きな問 |
| 題を投げかけるよになりました。こうした我が国における過去50年間の一連の湿気環境問題の根底には、一つに |
| は、敗戦後私たちが築き上げてきた経済発展の陰で、それまで長年にわたって蓄えてきた住まいづくりの工夫や |
| 暮らしの知恵を安易に捨て去ってしまったこともありますが、一方では、そうした生活環境の変化のなかで高断熱 |
| 高機密化された住まいでの新しい暮らし方の工夫が、つくり手の側にも住まい手の側にも十分に発展しないまま |
| に今日に至ったという事情があります。特に、住まいの通風、換気という点でそれを強く感じます。 |
| ■ 住まいの健康と湿気環境 |
| 気象条件と人の疾患との関係については、気象病と季節病という言葉があります。気象病というのはリウマチ、気 |
| 管支喘息、ベーチエット病などのように四季を通じて天候の変化や前線の通過などによって症状が起きたり悪化 |
| したりするもので、季節病とは、特定の季節に比較的多く発生したり悪化する傾向の見られる疾患のことをいいま |
| す。湿気環境という点から見ると、気象病は比較的に相対湿度との相関が大きく、季節病は相対湿度よりも絶対 |
| 湿度の方がより関係が強いようです。ちなみに中国漢方では、季節的な高湿度または低湿度による疾患の発生 |
| について、湿邪または寒邪という言葉を使っています。一般に、人の健康にかかわる気候要素としては、風、気温 |
| 、湿度、日射量、日照時間、気圧などがあります。人の皮膚には知覚点というものがあって、傷みを感じる部分を |
| 痛点、ものが触れるのを感じる部分を触点、温度を感じる部分をそれぞれ温点および寒点と呼んでいますが、大 |
| 気の乾湿を感じる湿点という知覚点はありません。そんなこともあって、人は湿気環境やその変化に比較的関心 |
| が薄いのかもしれません。図6は、ある寒冷地の高齢者介護施設の居住室の気温と湿度の月平均値の年変化を |
| 示したものです。右側の縦軸に相対湿度が示してありますが、12月から3月にかけての4カ月間の居住室内の相 |
| 対温度の月平均値が30%以下ということは、日平均値や瞬間値では甚だしく低い過乾燥状態が冬から春にかけ |
| て続いていたことになります。図7はくしゃみや咳によって空気中に飛んだインフルエンザウイルスの生存率と相 |
| 対湿度の関係を示したものです。50%以上の湿度では比較的早く死滅しますが、過乾燥状態の35%以下になる |
| と、ウイルスは驚くほど長く生き続けることがわかります。まして高齢者は抵抗力が低くなっていますからたまった |
| ものではありません。図8は、くしゃみの飛沫数の減少割合を推定した結果です。極端に換気量の少ない高気密 |
| の室内では、1人のくしゃみが多くの命を奪うことも十分考えられることをこれらの結果は示しています。住まいに |
| おける通風、換気の大切さを痛感させられる根拠がここにもあります。 |
| ■ 天然素材による調湿建材が健康を守り、文化財を誇る |
| 現在市販されている調湿建材の中には、すでに20年ほど前から、文化財の収蔵空間や展示空間の湿度調整を |
| 目的として、博物館、美術館、各種資料館などに施工されてすぐれた成績を収めているものもあります。 |
| 文化財の保存や展示については、その材質、形状を始めとして、保存、展示の目的、移動の有無、展示期間の |
| 長短などによって環境条件や調整方法を定める必要がありますが、化学薬剤や機械設備の多用は厳に慎まね |
| ばなりません。そうした点で、天然素材の調湿作用による湿気環境の調整は、省エネルギーを超える無エネルギ |
| ー的手段といえるでしょう。最近、こうした調湿建材の働きを住まいの湿気環境の調整に利用しようとする要求が |
| 高まったことはまことに喜ばしいことですが、先頃、官公庁から建築業界やさまざまな学会の研究者まで含めた |
| 住まいのアメニティ(快適環境)の提唱が、日本の住まい方になんらの方向づけをすることなく、一時的な言葉の |
| 流行に終わってしまったことを振り返ると、必ずしも喜んでばかりもいられないところがあります。最近の調湿建 |
| 材への関心の高まりを一時的なものに終わらせないためにも、この機会に、住まいのつくり手も住み手も、地域 |
| の環境風土に根ざした健康な住まいと住まい方の実現に向けて、広い視野に立った住まいの環境のしつらえ方 |
| を考えていきたいものです。 |
| ■ 調湿建材の働き |
| 調湿建材とは、その表面からの水分の吸放湿によって室内空気の相対湿度の甚だしい変化を和らげ、過度の湿 |
| 潤や乾燥を防ぐ動きをする内装用の建築材料で、人体や環境への悪影響が懸念される物質をいっさい使用して |
| いない材料のことをいいます。現在、市販されている調湿建材には、さまざまなものがありますが、素材別にわけ |
| ると土質系、石質系、木質系に大別することができます。素材系によりそれぞれ性能に特徴があり、目的によって |
| 使い分けることができます。調湿建材の性能は、断熱材料のそれとは異なり、特に外国からもたらされたもので |
| はなく、古くから私たちの身辺にあった天然の素材が備えていたごく普通の性質で、しかもその性能を意識して住 |
| まいの建材として使用したわけではないため、今ことさらに調湿建材といわれても、にわかには理解しがたい面も |
| あると思います。そこで最後に、調湿建材の動きを正しく理解するための四つのポイントを挙げてみるとおおむね |
| 次のようになります。 |
| ・ 第1のポイント |
| 調湿建材は乾燥のみを目的とした吸湿材料ではありません。 |
| 室内空気の極端な湿潤や乾燥を和らげるために、材料の吸放湿作用によって湿度変化を抑制して、室内空気を |
| ほどよい湿度に保つ動きをする内装用の建築材料です。住まいの室内を始め、小屋裏や床下の湿潤、結露対策 |
| は、本来、設計段階で配慮すべき問題です。 |
| ・ 第2のポイント |
| 調湿建材に即効性だけを期待することは誤りです。台所での煮炊きや浴室の出入りなどの際の急激な水蒸気の |
| 発生に対しては、むしろ換気によって対応する必要があります。しかも、どんなに早く効果が出てもすぐ働きが止 |
| まってしまってはだめで、春夏秋冬の1年間の季節的な環境変化のリズムにのって、室内空気の湿度調整の働 |
| きをするのが本当に優れた調湿建材です。 |
| ・ 第3のポイント |
| 調湿建材の動きは、季節により大きく異なります。一般に、冬季より材料自体の含水率が多くなる夏季の方がより |
| 大きな性能を発揮するので、日本のように夏の湿度が高くなるところに適しています。そして、春から夏にかけて |
| ためこんだ水分を使って冬に向かって乾燥を和らげてくれるのです。したがって、優れた調湿建材は即効性より |
| も湿気容量の大きいものということになります。 |
| ・ 第4のポイント |
| 内装用の調湿建材は、断熱材とは違い温度変化が加わる方向によって吸放湿効果が異なります。 |
| 一般に、室内気温の変化(内乱)による吸放湿よりも、外気温などの変化(外乱)によるほうが、内装された調湿建 |
| 材の働きは大きくなります。しかし、最近の住まいの外壁は高断熱になっていますから、通常は内乱的な気温変 |
| 動に基づく調湿作用ということになります。したがって、公表された調湿建材の性能値を見る場合には、その値が |
| 使用目的に合った正しい試験方法によって求められたものであるか否かを確かめる必要があります。 |
ご覧頂いているこちらのページは知識としてご紹介しておりますので、 商品につきましては取り扱いはしておりません。 販売商品はこちらのページのみとなります。 |
| トップページへ |
ウッドショップ 関口 群馬県甘楽郡下仁田町下仁田476-1 TEL:0274-82-2310 FAX:0274-82-4123 定休日は水曜日です。(詳細) |