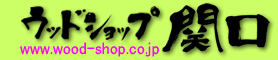

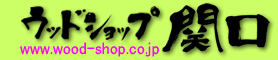 |
 |
| <<HOME| | 木材販売| | ご利用案内| | 運賃について| | 木の知識| | 作品例| | |FAQ | お問合せ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 植物には、脳も感覚器官らしきものもない。それでも何となく総体としてまとまっているのは、 | |
| 植物内部で何らかの情報の生成と内部コミュニケーシ ョンが行われていることを意味します。 | |
| そこで問題となるのは、植物の中のそれぞれの部分が、全体の状態をどうや って知るのかということ。 | |
| 私たちはまず、植物、およびその各部分が、環境 をどのように感知するかについて、植物をデバイスとして考え、 | |
| 実験してみました。竜場、磁場、熱、音などをイ ンプットして、アウトプット側では主 として生体電位、 | |
| つまり細胞の聞を流れる微弱なイオン流の変化を測定した。 | |
| それによって、刺激が植物の中をどう伝わってゆくかが明らかになると考えたわけです。 | |
| 刺激をある一枚の実に与えたとき、それが別の葉や根や茎の先端にどのように伝わるか、 | |
| よりミクロのレベルでは一枚の葉の中をどう伝わるかを、多くの電極を植物にセットして調べました。 | |
| ふつうなら、葉の先端に刺激を与えると、葉脈を伝わって刺激が連続的 に伝達されると予測されるのですが、 | |
| 結果的にはそうではなかった。順々に 伝わるわけでも道管を伝わるわけでもなく、跳躍的に伝達される。 | |
| 一枚の葉 に刺激を与えると、いきなり離れたところの葉に反応が出て、その後で近くの葉に反応が | |
| 出るということがある。予測したような植物体内部の伝達通路を通ってゆくというやり方をとっていないわけです。 | |
| 一方、根の研究では、根の周囲に形 成される全体的な電場の変化で情報を送るというやり方をとっている | |
| ということが少しずつわかってきた。 | |
| 植物全体でも、情報生成・共有は、電場や磁場のような |  高知県・足摺半島のスタジイ林 |
| 場の変化によって行われているのかもしれません。 | |
| ただ地上部の電場の測定は、空気中であるために、 | |
| 技術的な難しさがあります。また、根は生長するときに自分で | |
| 自分の方向を、自己ナビゲーションのよ うにして決めてゆく。 | |
| 自分で自分の道をつくるわけです。障害物があるとぶ | |
| つかってから曲がるのではなく、前もって曲がりながら | |
| 避けてゆく。もちろん途中でぶつかってしまうこともありますが | |
| 、その障害物と自分との関係の情報を刻々と生成し、 | |
| 自分で自分の形を変えてゆく。電場の変化がそれを | |
| 反映しているということは、ほぼ間違いないと思います。 | |
| 植物は、空間認知とともに、自分がその中でどのような | |
| ポジションにいて どのような形をしているのかという自己認知 | |
| を行っているようです。 | |
| 植物間では、これまでにエチレンのような化学物質による情報伝達が存在することが、報告されています。 |
| つまり毛虫などに葉を傷つけられるとエチーレンを発散し、それを受けとった別の植物が葉の中のタンニン成分を |
| 増やしているというものです。しかしそれはあくまでも成分をリアルタイムで測って得たのではなく、後で植物組織を |
| 化学分析して出した結果です。それに仲間と自分をどう関係づけるかという情報が、 |
| どのようにつくられているかがわからない。 森や林では、風の動きがかなりランダムなので、 |
| 情報がうまく拡散してゆくのかという堤間も積ります。もしうまくいっているのなら、そうしたケミカル・コミュニケーション |
| のプロセスは、非常に複雑だと思われます。私たちの、樹木間コミュニケーショ ンの実験では、自然林と人工林を |
| 対比させて、主幹の生体電位の流れを測定 しています。そこからの印象では、自然林では競争の原理だけではなく |
| 、共創の僚理が組み合って働いているようです。 |
| 一方、吉野の杉林のような人工林は、間伐しないと生きていけない。間伐さ れた樹木を肥料にしている。 |
| つまり間伐された樹木を排他していくという競争原理が中心にある。ちなみに、間伐 のプロはそのあたりを、 |
| 無意識のうち に見抜いているようです。だいたいの場合、生体電位がアブノーマルな波形を示すものが |
| 伐られている。均一で一様な波形を出していない樹木が、排除されてゆくのです。 |
| 自然林では、多くの樹種が同時に存在していますが、それぞれ20〜30本ぐらいからなる |
| 同じ生体電位の波形をもつグループを形成している。しかも同種間だけでまとまるのではなく、 |
| 異種間同士でグループをつくっている。季節によってメンバーの入れ替えが行われるのですが、不思議なことに、 |
| 夏になるとリセットされたように、一度全体が同じ波形を出す。それからまたグルーピングがはじまる。 |
| その際、グル ープ間を頻常に移動する木と、ほとんど移動しない木がいる。さらに奇妙なことに、 |
| グループといっても一箇所にまとまって形成されているわけではなく、かなり離れたところ同士で |
| グルー プをつくっている。植物には種によって原型的な生体電位の波形があり、ツバキならツバキのパターン、 |
| アオキならアオキのパターンと呼べるような共通したパターンが見られる。ところが山に入ると、その波形が消え、 |
| 新たにグループ共通の波 形がつくり出されます。植物に主体性のようなものがあるとするなら、一度自己否定して、 |
| 矛盾を解消しているという見方もできる。「一即多、多即一」 的な構造になっているのかもしれませんね。 |
| 一本の樹木でも、刺激を与えたときに反応する葉としない菓があり、しかも同じ葉がいつも反応するわけでもない。 |
| 無中枢でどこに中心があるかわからない。細胞レベル、組織レベル、器官レベルでも同様です。 |
| 個体レベルでも、反応するものとしないものが、森の中で地と図のように分離する。細胞 レベルから個体レベルまで |
| 同じシステムがはた働いているのかもしれません。これらは現象的にはリズムの引き込みや同調がかかわっている |
| とも言えますが 同調を引き起こすトリガーは何か、また同調したときに何が共有されるのかは、今後のテーマです。 |
| もしかすると植物たちは、自ら森を設計しているのかもしれない。今後は、電場以外の要素も含めて、 |
| 研究を進める必要があります。 |
| 植物に対する音楽の刺激においては、音庄が一つの大きな要素であり、60〜70デシベル以上ないと |
| 、有意な反応を誘発しない。音庄で道管が刺激されて、水が汲み上げられるために生長が早くなるという仮説も |
| ありますが、単にそれだけではない。振動しているところだけが反応するわけではないし、 |
| いちばん共振している部分が、生体電位の変化が最大というわけでもありません。 |
| 音楽と生育との関係を調べてみても、 実は、あまりにもファクターが多すぎてよくわからない。 |
| 結論は、音楽が生育にいいとも悪いとも言えないということ。条件さえそろえばいいのでしょうが、 |
| そろわないと枯れてしまうこともある。一概に音楽がいいというのは危険です。音楽を流すとスピーカーの方に向って |
| 植物が生長するとも言われますが、ホワイトノイズでもクラシッ クでも、生長が促進されることはあっても、 |
| 音の方に向うということはあまりない。確かに植物は音をサーチしていますが、音の方に進むわけではない。 |
| 基本的には、音楽も広義のストレスであって、生長が早くなったからとい って植物にとって本当にいい状態かどうか |
| はわからない。生長が早ければいいというのは、あくまでも人間的な視点です。 |
| もし仮にそういう視点から見るならば、リズミックな音楽の方がい い。1/f的なゆらぎをもっているクラシックや |
| せせらぎの音には、反応は出ない。逆にいうと植物は、そういう音にこそ安らぎを感じているのかもし れません。 |
| また、どんな音楽でも植物の中で一度コードがかえられていると思います。 |
| 植物なりの音楽の読みとり方があるのではないか。人間が三拍子といっていても、植物の中ではもっと |
| ロングレンジのリズムに変えられている可能性があります。 |
| さきほどふれた杉林の間伐のプロの人たちは、おそらく森の中に立ったと きに植物に同化し、 | |
| 直観的に森から排除された杉を選んでいる。私たちの体験からいうと、自然林は入り込みやすく、 | |
| 人工の杉林は美しいけれど中に入 ってみると無味監燥で窮屈。視覚附な印象もありますが、それだけでも | |
| なさそうです。そういうことと樹木のネッ トワークを結びつけて考えると、面白いかもしれません。 | |
| 気配というのは、自分がある場所に入ったときに、そこが自他非分離的な空間であるかどうか | |
| ということとかかわっていると思います。人工林は自他分離的ですが、間伐のプロはそういう場所でも | |
| 非分離的な状態になれる。私たちがある場所に入ったとき異様な感じがするというときは、 | |
| その場所を非分離的に見ている。そういうことを研究するには、 |  富士山、青木ケ原樹海のコメツガ |
| 人間の内側を計測しなければならない。 たとえば人と人とが | |
| 会話をしているケースでは、そこに相互引き込みが起こり両者が | |
| 同調しているかどうかを見るだけではだめで、そのプロセスが | |
| 内側からどのように創出されているのかを計測する必要がある。 | |
| 脳波や心拍だけの測定では不足で、リアルタイムに | |
| 情報がどのようにつくられているかがん問題になる。 | |
| そういう同時性であるかとか同場所性であるかということが、 | |
| これからの研究の重要なテーマになるはずです。 | |
ご覧頂いているこちらのページは知識としてご紹介しておりますので、 商品につきましては取り扱いはしておりません。 販売商品はこちらのページのみとなります。 |
| トップページへ |
ウッドショップ 関口 群馬県甘楽郡下仁田町下仁田476-1 TEL:0274-82-2310 FAX:0274-82-4123 定休日は水曜日です。(詳細) |