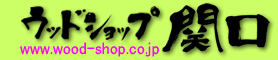

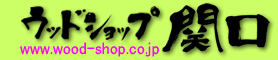 |
 |
| <<HOME| | 木材販売| | ご利用案内| | 運賃について| | 木の知識| | 作品例| | |FAQ | お問合せ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 木材を使って、様々な楽器が作られています。 身近なところでは、ギターやピアノ。日本の楽器では、琴、琵琶。三味線や太鼓も胴は木材です。 これらの楽器では適材適所とう言葉どおり、この楽器にはこの木材というように、 ある選ばれた木材が使われています。 ここでは、楽器にはどのような木材が使われているか、 またその様な木材はどの様な音響的性質を持っているかなどについて説明します。 また、化学処理などを使った新しい楽器用材料の開発や小径の スギ丸太からのピアノ響板材料の開発についても紹介します。 |
| 楽器の音には弦の振動を増幅する弦楽器であるか、 管の中の空気の振動が音となるがん楽器であるか、といったような 音の出方やそれに関わる構造が関係しています。 |
| しかし、よく聞いてみると、面白い事に金属を使った楽器にはどことなく金属の音色が、また プラスチックを使った楽器には、プラスチックの音がするものです。 |
| 木製楽器も同様で、一般には柔らかい暖かな音が木の楽器の特徴のようです。 |
| この様な木の音色は、木材のどのような性質に因るのでしょうか? |
| 木材の音響的性質について、金属のそれと比較してみると、 材料の中を伝わる音の速さや振動応答の速さは変わらないのに、 木材は金属の何倍も振動を吸収することがわかります。 |
| 適当な振動吸収が、人間の耳にとって優しい音を作るようです。 |
| もっとも、あまり振動吸収が大きいと、振動が材料で吸収されてしまい、音が出てこなくなってしまうのですが。 |
| また木材には、板として振動する時に、高い周波数の成分はあまり放出しない性質もあります。 |
| 打音や減の擦音には、かなり高周波までの成分が含まれているのですが、これらは木材を通り抜ける時に、 適当に吸収されます。 |
| 木材は一般に軽くて、よく振動することから、楽器材料に適しているといえます。 |
| しかし、どの木材を使ってもよい、という訳ではありません。 |
| 長い時間をかけて、楽器製作者は、それぞれの楽器に適した木材を選び出してきました。⇒表 |
| 例えば、バイオリンやギターの表板、ピアノの響板には、 イツトウヒあるいはシトカスプルースといった針葉樹が使われています。 |
| これらの木材は、木材の中では軽くて、音速が早く、そして振動吸収の少ない性質を持っており、 弦の振動に素早く反応し、効率よく音を放射します。 |
| ギターではベイスギも使われてますが、この木材はドイツトウヒよりもっと振動が少なく、その関係で、ベイスギギターは大きく、華やかな音をしています。 |
| ギターとバイオリンの材料の比較にも、大変興味深い点があります。 |
| いずれも、減の振動を木材が増幅する弦楽器です。 |
| 弦の振動が最初に伝わる表板には、どちらの楽器もドイツトウヒを用いますが、 表板と共に胴部を形成している裏板には、バイオリンはカエデを、 ギターはブラジリアンローズウッド(ハカランダー)をそれぞれ使用しています。 |
| カエデは、木材の中ではもっとも振動吸収が大きい部類に属しており、 一方、ブラジリアンローズウッドはドイツトウヒよりさらに振動吸収が少ない材料です。 |
| つまり、裏板材料として、バイオリンでは振動吸収の大きい木材が、 ギターでは振動吸収が少ない材料がそれぞれ好まれているというわけです。 |
| 弓からエネルギーが継続して供給される場色因と一度の弦の振動が、 振動エネルギーのすべてとなるギターでは、裏板に求められる音響特性が異なるという事でしょうか? |
| バイオリンについて考えてみると、音の増幅にはドイツトウヒが主として関わっており、
カエデは音を吸収することで音色の形成に積極的に寄与している様に思われます。 |
| この点は今後の研究課題です。 |
| 上に述べたように、ピアノの響板あるいはバイオリン、ギターの表板には、 振動吸収の小さい木材が経験的に選別されてきました。 |
| 材料に吸収される振動エネルギーが少なければ、 それだけ音響変換効率に優れ、音量の豊かな楽器になることから、 弦楽器の音質向上には振動吸収のさらに小さい木材が有用であると思われます。 |
| この様なことから、化学処理による木材の振動吸収の低下、 化学処理木材を用いた楽器作りを試みました。> |
| これまでに、ホルマール化処理(ホルムアルデヒドにより水酸基間に架橋構造を形成)や 低分子量フェノール樹脂含処理、レゾルシンを細胞壁中に含浸後、 ホルムアルデヒドと反応させて樹脂かされるレゾルシン・ホルムアルデヒド処理などにより、 少ない重量増加率(比重の増大を抑制)で振動吸収が木目方向で 30〜40%、木目に直角方向で40〜50%も低下することが明らかになっています。 |
| また、これらの処理は、いずれも木材の吸湿性を半分にまで低下させ、 志津と変化に対し、音響特性を安定させることができます。 |
| ホルマール化処理については、実際のバイオリンについて処理の効果を検討したところ、 音のつや、響きなどが向上することが明らかになりました。 |
| また、レゾルシン・ホルムアルデヒド処理については、 クラッシックギターにおいて実用化され、処理により音量が増大すると共に 音の立ち上がりがよくなることが知られています。 |
| 近年、良質の楽器材料の確保は、環境問題と密接に関わり年毎に困難になっています。 |
| 森林資源を守りながら、その一方で楽器が関わる文化を継承していくためには、 早く成長し、再生が容易な継続的森林資源を材料とした音響材料の開発が求められています。 |
| この様な観点からスギ小径丸太(20〜30年生)を原材料とした ギター、ピアノ材料の製造を試みました。 |
| スギのロータリーレースベニヤに低分子量フェノール樹脂を含浸し、繊維方向をそろえて蓄積した後、 熱圧締すると、圧締時の圧力を調整することで、ギター表板用ベイスギ材と同等の音響特性を有する 低比重から、ギター裏板用ブラジリアンローズウッド材の代替となりうる高比重材まで製造できました。 |
| さらに、この材料を積層複合することで、ピアノ響板用スプルース材と同等 あるいはそれより高い比弾性率を有する材料に変換できることもわかりました。 |
 |
ご覧頂いているこちらのページは知識としてご紹介しておりますので、 商品につきましては取り扱いはしておりません。 販売商品はこちらのページのみとなります。 |
| トップページへ |
ウッドショップ 関口 群馬県甘楽郡下仁田町下仁田476-1 TEL:0274-82-2310 FAX:0274-82-4123 定休日は水曜日です。(詳細) |